【用語解説】サーバー監視とは?企業のリスク回避と安定運用のための必須対策
更新日:2026-01-15 公開日:2024-04-11 by アツシバ
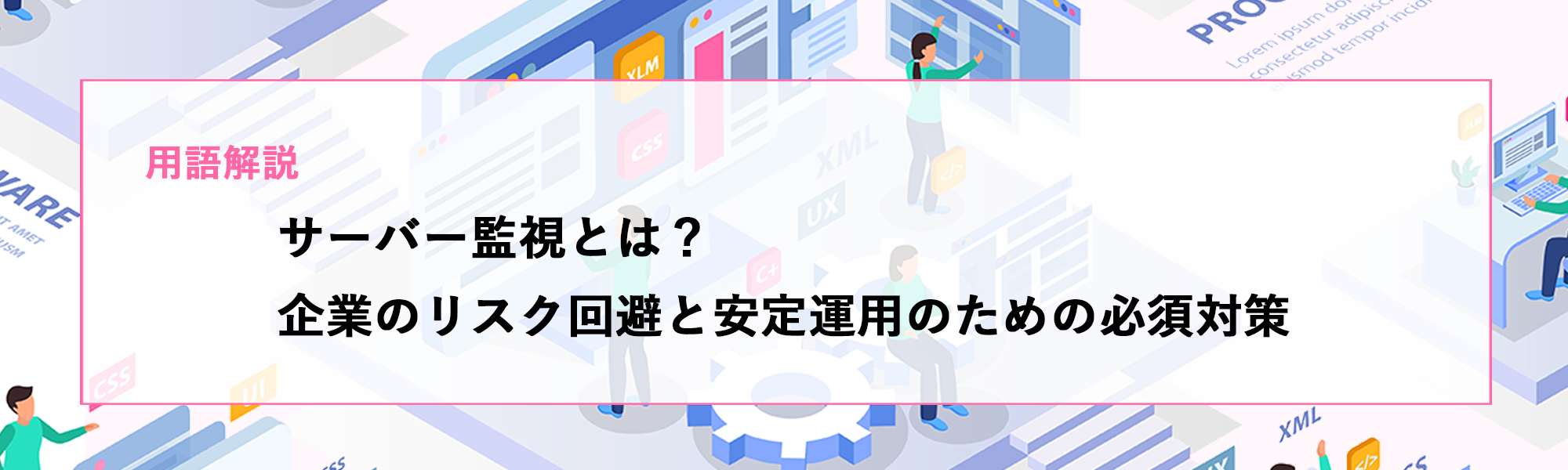
サーバー監視とは
サーバー監視とは、企業が運用するWebサイトやシステムの稼働状況を、24時間365日体制で継続的にチェックし、異常を検知して通知する仕組みです。
現代のビジネスでは、ホームページ、ネットショップ、顧客管理システムなどのITシステムが事業の中核を担っています。これらのシステムが停止することは、直接的な売上損失や企業の信頼失墜につながる重大な事態です。
なぜサーバー監視が必要なのか
事業損失の防止
システム停止がもたらす影響は、想像以上に深刻です。
具体的な損失例
・予約システムの障害で顧客満足度低下と競合他社への流出
・基幹システム停止により全社業務がストップ
このような事態を未然に防ぐことが、サーバー監視の最重要目的です。
顧客信頼の維持
「いつアクセスできなくなるかわからないサイト」では、顧客は安心してサービスを利用できません。安定したシステム運用により、顧客からの信頼を獲得し、競合他社との差別化を図ることができます。
業務効率の向上
監視により問題を早期発見することで、大きな障害になる前に対処可能です。結果として、復旧にかかる時間とコストを大幅に削減できます。
どのような会社にサーバー監視が必要か
特に重要性が高い業種
| ネットショップ運営企業 | 1分の停止も売上に直結するため |
| 予約システム利用企業 | 美容室、レストラン、クリニックなど |
| 会員制サービス運営企業 | 顧客情報を預かる責任がある |
| BtoB企業 | 取引先への影響を考慮する必要がある |
会社規模は問わない
「うちは小さい会社だから大丈夫」という考えは危険です。規模に関わらず、ビジネスでITシステムを利用している企業にはサーバー監視が必要です。
サーバー監視の主要機能
基本監視項目
| サイトの稼働確認 | ホームページが正常に表示されるか |
| 応答速度監視 | ページの表示が遅くないか |
| サーバー状態監視 | コンピューターに負荷がかかりすぎていないか |
| セキュリティ監視 | 不正なアクセスがないか |
代表的なサーバー監視ツール
監視項目や通知機能を実現するために、多くの企業では専用ツールが利用されています。ここでは代表的な監視ツールを紹介します。
【統合監視ツール】
Datadog
クラウドネイティブな統合監視プラットフォーム。サーバー、コンテナ、アプリケーションを横断的に可視化し、AWS・Azure・Google Cloudなど複数の環境を一元管理できます。
Zabbix
オープンソースの総合監視ツール。自社構築でコストを抑えつつ、ネットワーク機器からサーバーまで幅広く監視できるのが特徴です。
【クラウド環境特化型】
AWS CloudWatch
AWS環境の標準監視サービス。CPU使用率やディスクIO、コスト管理などのメトリクスをリアルタイムで可視化できます。
Azure Monitor
Microsoft Azureの監視基盤。ログ分析やアラート設定が容易で、セキュリティ監視との連携も可能です。
これらのツールを活用することで、障害の早期発見やリソースの最適化が可能になります。監視対象や運用体制に応じて、クラウド特化型・オンプレ統合型など最適なツールを選定しましょう。
通知機能
異常を検知した際の連絡方法も重要です。
| メール通知 | 詳細な状況報告 |
| 電話 | 緊急時の確実な連絡 |
| チャットツール連携 | チーム全体での情報共有 |
クラウド環境でも監視は必要不可欠
よくある誤解:「クラウドなら監視不要」
「クラウドはサービス事業者が管理してくれるから、監視は必要ない」と考える方がいらっしゃいますが、これは危険な誤解です。
実際に起きている問題
・セキュリティ設定の不備で顧客情報が外部に公開
・自動拡張機能の誤作動で想定外のサーバー費用が発生
・アプリケーションの不具合をクラウド事業者の問題と誤認し、対応が遅れる
責任共有モデルの理解が重要
クラウドサービスには「責任共有モデル」という重要な概念があります。この考え方を理解せずに監視を怠ると、重大な障害や情報漏えいにつながる恐れがあります。
責任共有モデルとは
クラウドサービスにおいて、セキュリティと運用の責任をクラウド事業者と利用企業で分担する考え方です。
クラウド事業者(AWS、Azure、GCPなど)の責任範囲
|
利用企業の責任範囲
|
よくある勘違いと現実
間違った認識:「クラウドを使えば、すべての管理をクラウド事業者がやってくれる」
現実:システムが止まった時、クラウド事業者から「お客様のアプリケーションの問題です。インフラは正常に動作しています」と言われるケースが多発しています。
実際の対応例
| データベースの接続エラー | → | 「設定の問題です」 |
| Webサイトが重い | → | 「アプリケーションの最適化が必要です」 |
| セキュリティインシデント | → | 「権限設定を確認してください」 |
つまり、利用企業の責任範囲で発生した問題は、自社で監視・対応する必要があります。
クラウド特有の監視項目
| コスト監視 | 想定外の課金を防ぐ(月次請求が急に10倍になるケースもある) |
| 自動拡張機能の確認 | アクセス増加時の対応が適切か |
| セキュリティ設定の管理 | 設定変更により意図せず外部公開されるリスク |
| サービス制限の管理 | API呼び出し制限に達してサービス停止するリスク |
監視方法の選択肢
システムの規模や業務の重要度により最適な選択肢は異なります。
自社対応は初期費用を抑えられますが、専門性と継続性の観点から、多くの企業で専門企業への委託が選択されています。
自社対応
メリット
- 初期費用が抑えられる
デメリット
- 専門知識が必要
- 24時間対応が困難
- 設定ミスのリスク
専門企業への委託(推奨)
メリット
- 専門知識と豊富な経験
- 24時間365日の監視体制
- 適切な設定による誤報の防止
- 最新の技術トレンドへの対応
デメリット
- 月額費用が発生
まとめ
サーバー監視は、オンプレミス・クラウドを問わず、現代企業が事業継続性を確保するために欠かせない投資です。特に「クラウドだから安心」という思い込みは非常に危険であり、責任共有モデルを理解した上で、クラウド環境では従来以上に高度な監視が求められます。
システム障害による損失を考えれば、監視サービスへの投資は十分に正当化されます。また、クラウド特有のリスク(コスト超過、セキュリティ設定ミス、責任範囲の混乱)に対しては、専門知識を持った監視サービスが不可欠です。
自社での対応が困難な場合は、クラウド環境に精通した経験豊富な専門企業への委託を推奨いたします。適切なサーバー監視により、安定したビジネス環境を構築し、競合他社との差別化を図ることができます。
まずは現在のシステム状況を把握し、特にクラウド環境をご利用の場合は責任共有モデルを正しく理解した上で、最適な監視の検討から始めることをお勧めいたします。
サーバー監視の専門的なご相談を承っております
オンプレミスからクラウド環境まで、責任共有モデルを踏まえた適切な監視ソリューションをご提案いたします。現状分析から運用開始まで、一貫したサポート体制で貴社のビジネス継続性向上を支援いたします。




